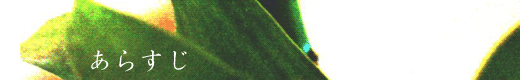
生い立ち
竹取翁が山で、光る竹の中から幼子を見つけた。三寸ほどの大きさだったが、媼に育てさせたところ短期間のうちに美しく成長する。翁は竹から黄金を得て豊かになり、家中が姫の放つ光に満ちた。なよ竹のかぐや姫と命名しての三日間は、男たちが呼ばれ盛大な宴が催されるのだった。
『竹取物語』はふつう王朝物語の祖であり、原形であるとみなされている。むろん、単に成立の早さによるだけでなく、むしろ詩情あふれる主題性によってそうなのである。ただし、作中の語源譚などに指摘されるイロニカルな姿勢は、この物語の全く別の一面を物語っている。それらを総合したところに『竹取物語』の虚構性の特質をみるべきなのだろう。
難題譚
姫に求婚しようとする男たちが大勢おしかけるが、相手にされない。多くはあきらめて去り、さいごに色好みで鳴らす五人の貴公子だけがのこる。彼らのねばりに、翁はついに根負けして、姫に結婚をすすめはじめた。姫は翁との論争のすえに、五人に難題を出し、その結果で相手を決めたいとせざるをえなくなるのだった。
昇天
帝と心を通わせて三年目、春ごろから、かぐや姫は月を見て物思いにふけることが多くなる。八月十五夜を前にして、翁に自らの素性をあかし、離別の日が近いことを泣きながら打ちあけるのだった。翁は驚き悲嘆にくれつつも、月からの迎えを撃退すべく帝に援軍をたのみ、当日を迎える。が、それも空しく、姫は翁と帝への形見として手紙と不死の薬をのこし、昇天してしまう。
富士の山
その後、翁と媼は泣き惑い、病臥する。兵をひきいて戻った中将から報告を受けた帝も、形見をまえにして悲嘆に沈むが、いっぽう、大臣、上達部たちから、天にいちばん近いのは駿河の国にある山だと聞き、嶺で不死の薬を燃やすよう勅使に指示した。薬を焼いた煙は、いまでもその山(富士山)から立ちのぼっている。
※ 小嶋菜温子・島内景二 「竹取物語を読む」 別冊国文学No.34 1988より










 Use
Use Support
Support My Library
My Library
 About Us
About Us