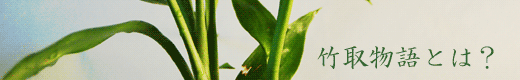
竹取物語はいつ書かれたか?
“『竹取物語』は九世紀末か十世紀の初めに書かれた。物語の結末に「その煙、いまだ雲の中へ立ち昇るとぞ」とあり、富士山はまだ活火山であったことがわかる。創造された時期を知るには大変貴重な手掛かりである。『古今和歌集』の仮名序に「今は、富士の山も煙たたずなり」となっているので、『古今和歌集』が編纂された905年以前に富士山は活火山でなくなったことが明らかである。そうすると、『竹取物語』は遅くて905年までに出来たことがわかる。創作された年ははっきりしないが、日本の最も古い物語であるに違いない。『源氏物語』の中で、『竹取物語』は『物語の出(い)で来はじめの祖(おや)なる竹取の翁』として紹介されている。・・・”
ドナルド・キーン/川端康成著 『竹取物語:The Tale of the Bamboo Cutter』 講談社 1998序文より
物語文学とは?
平安から鎌倉時代に盛行した文学形態。口承文芸を母体とする<竹取物語>に始まるとされる。作り物語の流れは伝奇的なものから次第に写実性を獲得した。一方、和歌の詞書から発展して<伊勢物語>を代表する歌物語が成立、さらに作者の経験に即した<蜻蛉日記>のような日記文学の系譜があり、これらを発展的・統一的にうけついで<源氏物語>が出現する。<源氏物語>以後、狭衣物語・堤中納言物語等が数多く書かれたが<源氏物語>とは別の領域をひらくには至らず、中世の擬古物語にうけつがれ、<大鏡>などの歴史物語、<今昔物語集>以下の説話文学が台頭する。
(平凡社 マイペディア2003 電子辞書版より)










 Use
Use Support
Support My Library
My Library
 About Us
About Us