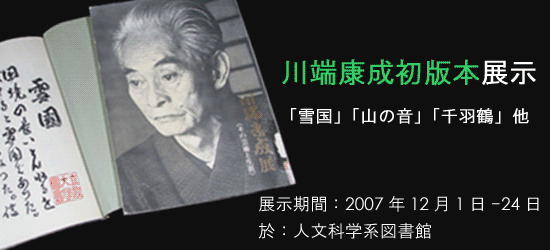 |
||

1968年10月17日、スウェーデン・アカデミーは、日本人作家としてはじめて川端康成にノーベル文学賞を授与すると報じた(東洋ではインドの詩人タゴールに次いで二人目)。このときアカデミーが受賞理由にあげたのは「すぐれた感受性で日本の心の神髄を表現するその叙述の巧みさ」であり、それを具現する代表作に掲げられたのが『雪国』『千羽鶴』『山の音』だった。また、川端自身も受賞決定直後のインタビューで、サイデンステッカーという優れた翻訳者、三島由紀夫という「若きライバル」がいてくれたからこそと謙遜しつつも、自分の文学がもっている「日本文学の伝統の匂い」(「サンケイ新聞」1968・10・18)が認められたことを率直によろこんでいる。同年12月10日にストックホルムで行われた記念講演のタイトルを「美しい日本の私―その序説」としたのも、そうした他画像を引き受けてのことであろう。かつて、川端の文学を「冷たい理智」「美しい抒情」などと賞讃する世人を「化かされた阿呆」とよんだのは小林秀雄だが、川端は、自ら進んで西欧から眼差される「日本」という衣装をまとってみせることで、「伝統」や「美意識」の継承者という場を占めるに至ったのである。のちに、日本人として二人目のノーベル文学賞を受けた大江健三郎が「あいまいな日本の私」という記念講演を行い、「独自の神秘主義」に没入した川端を皮肉ったのは1994年のことだった。
(文学部文学科日本文学専修教授 石川巧)










 Use
Use Support
Support My Library
My Library
 About Us
About Us