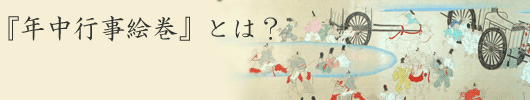
『年中行事絵巻』について
「年中行事絵巻」は、後白河院(1127-1192)の下命によって作られ、もとは60巻の巻物にまとめられていた、と言われている。しかし原本は近世初期のころに惜しくも炎上してしまった。その後住吉如慶(1599-1670)・具慶(1631-1705)父子によって写された模本16巻などが現在に伝えられている。「年中行事絵巻」はもともと、一月から十二月までの宮廷主要行事のすべてを絵画にしたものであった。しかし現存の絵巻では七~九月、十二月はほとんど残っていない。立教大学図書館所蔵の絵巻は江戸末期作のものと思われ、第一巻の「朝覲行幸」だけが描かれている。
「朝覲行幸」とは?
「覲」は、謁見の意味。年の初めに、天皇が父帝、または母后の宮に行幸して、拝賀する儀式。宮廷の新年の年中行事は、一日に四方拝、朝賀、元日節会(がんじつのせちえ)などが行われ、ついで二日に、二宮大饗(にぐうのたいきょう)、朝覲行幸(ちょうきんぎょうこう)などが行われた。
※『日本絵巻大成』第8巻(中央公論社1977)を参考に作成しました。










 図書館を使う
図書館を使う 学修・教育支援
学修・教育支援 My Library
My Library
 図書館の紹介
図書館の紹介