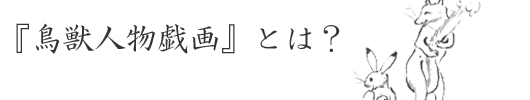
『鳥獣人物戯画』とは?
京都・高山寺蔵の四巻から成る絵巻。国宝。12世紀中期~13世紀中期の制作とされ、四巻はそれぞれ制作時期と筆を異にしている。「鳥獣戯画」ともよばれる。筆者は鳥羽僧正(とばそうじょう)覚猷(かくゆう)(1053-1140)と伝称されるが確証はない。
擬人化された動物の諸態や、人間の遊びに興ずるさまが描かれている。各巻とも詞書(ことばがき)を欠き、絵に説かれる内容、意味が明らかでなく、種々の解釈がなされるが定説をみない。絵はいずれも墨一色の描線を主体とした白描(はくびょう)画で、動物や人物、草木などを闊達(かったつ)な筆で巧みに描出している。筆者や制作時期が不明瞭であるものの、『鳥獣人物戯画』からは、密教図像の作画などで習得された、当時の高度な描線の筆技を知ることができる。
各巻紹介
甲巻
最も優れているといわれる巻。猿、兎(うさぎ)、蛙(かえる)などが人間をまねて遊ぶ模様が描かれている。濃淡、肥痩(ひそう)、強弱の変化をつけた抑揚豊かな描線の筆技が絶妙で、日本の白描画の白眉(はくび)といえる。
乙巻
馬、牛、鶏、獅子(しし)、水犀(みずさい)、象、それに麒麟(きりん)、竜など空想的なものを含めた各種動物の生態が描かれている。
丙巻
僧侶(そうりょ)や俗人が勝負事に興ずるありさまと、猿、兎、蛙などが遊び戯れるさまが描かれている。描線が繊細でやや闊達さを欠く。
丁巻
僧俗の遊び興ずるさまが描かれている。
※日本大百科全書(ニッポニカ)を参考に作成しています。










 図書館を使う
図書館を使う 学修・教育支援
学修・教育支援 My Library
My Library
 図書館の紹介
図書館の紹介